こんにちは、土地家屋調査士のはるです。
土地家屋調査士試験は、法務省管轄の国家資格で、合格率は例年10%前後の高難易度といわれる国家試験です。
勉強内容は法律だけでなく、計算や作図などもあり、幅広い知識や技能が求められ、独学ではハードルが高いと感じる人も多いでしょう。
しかし、実際には独学でも十分に合格を目指すことは可能です。
ポイントは「正しい教材選び」と「効率的な学習手順」です。
近年の土地家屋調査士試験では、出題傾向の変化もあり、今まで以上に理解重視・応用力重視の出題が増えています。
この記事では、私自身の体験を踏まえつつ、独学での合格を目指す方に向けて、最新のおすすめテキストとその効果的な使い方をご紹介します。
さらに、費用を抑えながら効率よく学べる予備校の単科講座についても、具体的に解説していきます。
後半では私のおすすめテキストを使用した勉強スケジュールを紹介していますので参考にしてください。
土地家屋調査士試験の全体像と独学の難易度
土地家屋調査士試験は、筆記試験(択一式・書式(記述式))と口述試験に分かれています。
口述試験は筆記試験に合格しなければ進めませんが、基本的に落ちることはないので筆記試験のことだけを考えれば大丈夫です。
- 択一式試験:法令等の知識を問う択一式問題
- 書式(記述式)試験:実際の登記申請書や図面作成を伴う実務型問題
- 口述試験:面接形式で行われる口頭試問
書式(記述式)試験は土地家屋調査士試験の最大の特徴であり、独学者にとって特に難関となります。
書式(記述式)試験は知識だけでなく、長い問題文を読み、状況を把握する力や、答案構成力・計算力・作図力などが求められるため、単にテキストを読むだけでは対応できません。
土地家屋調査士試験の学習ステップ(独学者向け)
土地家屋調査士試験を独学で進めるうえで、まず大切なのは 「適切なテキストを選ぶこと」 と 「正しい順序で学ぶこと」 です。
土地家屋調査士試験用の市販テキストには難解なものも多く、闇雲に読み進めても効率が上がらず、途中で挫折してしまう人も少なくありません。
そこで、ここでは独学で最短合格を目指すための学習ステップを4段階に分けて紹介します。
具体的には、
①入門→②択一式対策 → ③書式(記述式)対策→ ④実践演習
という順で進めるのが理想です。
- 入門
- 択一式対策
- 書式(記述式)対策
- 実践演習
| 学習ステップ | 学習目的 | テキストの種類 |
|---|---|---|
| 1、入門 | ・土地家屋調査士試験の概要理解 ・全体像をつかむ | 入門書 |
| 2、択一式対策 | 法令知識(民法、不動産登記法、土地家屋調査士法など)を理解・記憶する | ・インプット用テキスト ・アウトプット用テキスト |
| 3、書式(記述式)対策 | ・関数電卓を使用した計算方法の習得 ・作図方法・申請書の書き方の習得など | ・計算、作図用テキスト ・登記申請書用テキスト |
| 4、実践演習 | 本試験形式に慣れる | ・過去問集 ・演習書 |
このような流れで進めることで、独学でも「何を」「どの順に」学べばいいかが明確になります。
特に、書式(記述式)は実技要素が強いため、計算する・書く・描くという「手を動かす学習」を意識することが、 最短合格への近道です。
独学に最適なテキストとその特徴【2026年対応版】
学習ステップを理解したら、次はテキスト選びです。
土地家屋調査士試験は範囲が広く、教材選びを間違えると効率が大きく下がります。
特に独学者にとっては、「わかりやすさ」と「網羅性」 の両立が重要です。
土地家屋調査士試験の市販されているテキストは残念ながら数が少なく、優れたテキストがほとんどないのが現状です。
ここでは、独学で合格を目指す方に向けて、学習の流れを踏まえつつ、独学でも効率よく学習を進めるためのおすすめテキストを紹介します。
1、入門書で全体像をつかむ
土地家屋調査士になりたいと思ったらはじめに読む本
著者:木村真弓(LEC東京リーガルマインド専任講師)
定価:2,420円(税込)

おすすめ度★★★
土地家屋調査士という仕事の“本質”や“魅力”を、受験生の視点でわかりやすく解説した入門書です。
これから受験を考えている人にとって、「本当に自分に向いているか?」「どんな働き方なのか?」を理解できる、独学者のスタートに最適な1冊です。
本書の特徴
土地家屋調査士の仕事像が明確になる入門書
- 業務内容・働き方・やりがい・キャリアなどを“初心者向けの文章”で解説
- 「なぜ土地家屋調査士を目指すのか?」という根本のモチベーション形成に役立つ
専門用語を極力使わず、読みやすさに特化
- 法律・測量などの難解な話から入らないため、初学者でも抵抗感がない
- ゼロから土地家屋調査士を目指す人に最適
仕事・キャリアの実体験を交えた解説でモチベーションが上がる
- 実務家のストーリーが記載されており、勉強に疲れたときに読み返すと気持ちが立て直せる
- 資格取得後のイメージが持てるため、勉強の目的が明確になる
試験制度の概要が整理されていて、学習の最初のガイドブックになる
- 何を勉強すべきか、どの科目が重要かがシンプルに理解できる
- 初学者が抱く「自分でもできるのか?」という不安が解消されやすい
補訂版 中山祐介の土地家屋調査士試験合格講座 まず押さえたい!択一式攻略テキスト
著者:中山祐介(アガルートアカデミー専任講師)
定価:2,420円(税込)

おすすめ度★★★
土地家屋調査士試験の“択一式対策”に必要な知識だけを厳選した、独学者にとって非常に扱いやすい基礎レベルの対策テキストです。
特に、法律科目が苦手な人や本格的テキスト前の独学者に相性が良い一冊です。
本書の特徴
択一式に必要な重要論点だけを厳選した入門テキスト
- 民法・不動産登記法・土地家屋調査士法など、頻出分野を重点的に整理
- “まず覚えるべき範囲”を明確にし、最短ルートで得点力を上げられる
中山祐介氏独自の「理解重視の解説」
- 単なる暗記ではなく、「なぜそうなるのか」を丁寧に説明
- 条文のつながりがわかりやすく、法律が苦手な初学者でも読みやすい
図表・具体例が多く、法律知識が定着しやすい構成
- 難しい法律用語をかみ砕いた説明が多く、理解のハードルが低い
- 紙面デザインが視覚的で、学習効率が高い
土地家屋調査士試験の“出題傾向”を踏まえた構成
- 実際の試験で狙われるポイントに絞っているため、ムダがない
- 出題方針に沿った論点整理がされている
独学者向け活用ポイント
択一式の“基礎固め”に最適な1冊
- 本格テキストに進む前に本書で全体像を掴むとスムーズ
- 初めて法律を学ぶ初学者の入門書として優れている
法律が苦手な受験生の“つまずき防止テキスト”として機能
- 特に民法・不動産登記法の全体像をつかみたい人に向いている
- 難しい論点を整理し直す“再学習用テキスト”としても活躍
短期間で択一式の得点力を上げたい人に効果的
- 独学で効率重視なら本書のような“最重要論点だけ”を扱う教材はメリットが大きい
ここからはじめる 土地家屋調査士速習テキスト
著者:土地家屋調査士受験研究会
定価:3,740円(税込)

おすすめ度★★☆
土地家屋調査士試験の独学をこれから始める人にとって、本書は本格テキスト前の「最初に読むテキスト」として相性の良い一冊です。
試験範囲の全体像を短時間で把握でき、学習計画を立てる基礎づくりに役立ちます。
補訂版 中山祐介の土地家屋調査士試験合格講座まず押さえたい! 択一式攻略テキストよりはやや難しく感じるかもしれません。
本書の特徴
土地家屋調査士試験の全体像が理解しやすい速習テキスト
- 民法・不動産登記法・土地家屋調査士法などの択一式対策だけでなく、書式(記述式)対策など、受験科目の要点をコンパクトに整理
- 多くの独学者が悩む「どこから手をつけるべきか?」を解消
専門用語を使いすぎない“入門書”として読みやすい構成
- いきなり難解な条文や判例に触れないため、初学者でも挫折しにくい
- 法律学習が不安な人でもスムーズに読み進められる
図表が豊富で、測量や登記手続きの流れが視覚的に理解できる
- イラスト・図解が多く、最頻出論点のイメージがつかみやすい
短期間で全範囲を“ざっと回す”ことができる
- 忙しい社会人やスキマ時間で勉強したい人に向いている
独学者向け活用ポイント
本格テキストに入る前の“準備運動”にちょうど良い
- 本格的な教材に行く前に基礎用語を理解できる
- 初学者の最大の壁である“用語の難しさ”を緩和してくれる
中だるみの時期の“基礎リセット”として再読しやすい
- 学習に行き詰まった時、基礎を短時間で復習するのに向いている
- 択一式や書式(記述式)対策として、全体像を再確認できる
2、入門書が終わったら本格的な択一式対策テキストで学ぶ
インプット用テキスト
土地家屋調査士受験100講〔Ⅰ〕理論編 (不動産登記法と調査士法)
著者:深田静夫(早稲田法科専門学院)
定価:5,170円(税込)

おすすめ度★★☆
不動産登記法・調査士法の「根本理解」を重視したロングセラーテキスト。
長年の受験指導で蓄積された知識が体系的に整理され、初学者でも条文の背景から理解できる。
市販のテキストの中では不動産登記法・調査士法の理解を“根本から固めたい独学者”に最適の本格派理論テキストです。
体系的で網羅性が高く、調査士試験の法律科目をしっかり学びたい人に向いています。
本書の特徴
不動産登記法と調査士法を体系的に学べる専門テキスト
- 項目ごとに体系立てて解説されており、条文のつながりや背景が理解しやすい
- 独学者が陥りがちな“部分暗記”ではなく“構造理解”につながる
土地家屋調査士試験の頻出テーマを深く掘り下げて解説
- 本試験に頻出する主要論点を丁寧に整理
- 出題の背景にある法律構造や考え方まで踏み込んで説明されている
文章量は多いが、内容が濃く、辞書的にも使える
- 必要な論点がほぼ網羅されており、「分からない部分を戻って調べる」スタイルに向いている
- 長期的な受験勉強の“基本書”として活躍
独学者向け活用ポイント
本格的に不動産登記法を理解したい人の“理論の土台”になる
- 過去問や択一を解いていて「理由が分からない部分」を補強するのに最適
- 理屈を理解すると択一の正答率が大幅に上がる
(書式)記述式の背景理解にも役立つ
- 記述式問題は“理論を理解しているか”が点数を左右するため、本書は応用にもつながる
過去問では補えない“体系的理解”が身につく
- 独学者が苦手とする、条文や制度の関係性を把握しやすい
疑問点の解決に最適な“調べる用テキスト”として使える
- 学習中に「この登記はどんな根拠?」と思ったときに、戻って読み直すと理解が深まる
土地家屋調査士受験100講〔Ⅱ〕理論編 民法とその判例
著者:深田静夫(早稲田法科専門学院)
定価:4,840円(税込)

おすすめ度☆☆☆
上記シリーズの民法のものになりますが、こちらはあまりおすすめできません。
理由は、出版日が古いことと、初学者にはやや難解な内容だからです。
民法に関してのおすすめテキストは他資格用の市販テキストです。
-
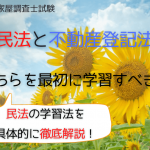
-
【土地家屋調査士試験】民法と不動産登記法どちらを最初に学習すべき?【民法学習法】
2024/1/8 新・合格データベース, 民法, 独学
こんにちは、はるです。 『土地家屋調査士試験に挑戦するぞ!』と決心はしたけれども、 どの科目から勉強を始めるべきかは、頭を悩ませる大問題ですよね。 今回の記事はこのような方の疑問にお答えします。 答え ...
重要
不動産登記法や土地家屋調査士法を学習する前に、先に民法を学習されることを強くおすすめします。
理由は簡単に言うと、「民法が基礎」であり、「登記法はその応用」といえる構造になっているためです。
登記は「権利に関する事実」の記録なので、そもそも 権利そのものの正しい理解(民法)がないと、登記法の意味が理解できない という構造です。
アウトプット用テキスト(インプット用テキストと併用すると記憶の定着や整理に効果的)
土地家屋調査士 択一攻略要点整理ノート Ⅰ・Ⅱ
著者:東京法経学院 編集部編
定価:22,000円(税込)※2冊セット販売
※書店等では販売しておらず、東京法経学院の公式サイトで購入可能です

おすすめ度★★☆
択一式で“最短スピードで得点力を上げたい独学者”に最適の、超効率型ポイント整理ノートです。
試験頻出論点だけを抽出し、「どこが出るのか」「どう覚えるか」を一目でつかめる実戦的テキストとなっています。
本書の特徴
「要点整理+練習問題」構成でインプットからアウトプットまで対応可能
「要点整理」部分で重要論点・条文・先例をコンパクトにまとめ、「練習問題」部分で5肢択一・穴埋め形式の演習を同じ講内で行える構成となっており、別々のテキストを用意せずに「知識を確認→問題演習」という流れを1冊で回せる点が大きなメリット
出題範囲が講(レクチャー)単位で分けられており、計画が立てやすい
出題範囲が講分けされており、「今日はこの講」「明日はこの講」というようにスモールステップで進められるので、計画管理・進捗管理しやすい構成
択一試験の頻出ポイントを徹底的に凝縮
- 民法・不動産登記法・土地家屋調査士法の重要論点を“出題される順番”で整理
- ムダな説明を省き、得点に直結する情報だけをまとめた構成
図表・まとめ中心で視覚的に理解しやすい
複雑な制度も図で整理されているため、記憶に残りやすく、独学者でも理解の手がかりをつかみやすい。
最新の試験傾向に対応
現在の本試験頻出テーマに合わせて改訂され、直近年度の傾向とも相性が良い
独学者向け活用ポイント
合格に必要な“学習水準・範囲”を明確に限定しており、学習のブレを防げる
独学だと「どこまで勉強すればいいか」「範囲が広すぎて手が付かないかも」という不安が出がちですが、このテキストでは「必要最低限+重点」として範囲設計されており、効率的に学べます
過去問学習の“事前マップ”として使うと効果絶大
- 要点を先に押さえてから過去問に入ることで、理解の速度が圧倒的に上がる
- 初見でつまづきやすい論点を事前に整理できる
苦手箇所だけすぐ見返せる“辞書的ツール”として使える
区分建物だけ弱い、土地家屋調査士法が苦手など、ピンポイントで補強したいときに短時間で復習できる
直前期の総仕上げに最適
試験直前の「抜けチェック」や「知識の棚卸し」に使いやすい構成
コンパクトで携帯しやすく、スキマ時間学習に最適
毎日数分ずつでも繰り返せるサイズ感で、通勤・移動中に“得点ポイントだけ”を確認できる
注意点
本書は要点整理ノートであり、以下の用途には向きません。
- 初学者が最初に読む入門書や基本テキストとしての利用
- 細かい理論を深く学ぶ目的
そのため、
基本テキストで項目ごとに理解する
→ 本書で出題ポイントを確認
→ 過去問で実戦力を固める
という使い方が最も効果的です。
新・合格データベース
著者:東京法経学院 編集部編
定価:33,000円(税込)※3冊セット販売
※書店等では販売しておらず、東京法経学院の公式サイトで購入可能です

おすすめ度★★★
新・合格データベースは非常におすすめのアウトプット用教材です。
-
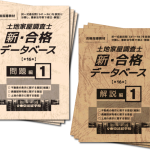
-
【2026年択一対策】新・合格データベースの特徴と使い方【東京法経学院】
2025/11/17 択一対策, 新・合格データベース
こんにちは、土地家屋調査士のはるです。 今回は択一対策で20問中、18問以上の逃げ切りを目指す方に必須の教材を紹介します。 それは東京法経学院から販売されている『新・合格データベース』です。 こちらの ...
3、書式(記述式)対策用のテキスト(勉強は「手を動かす」がポイント)
中山祐介の土地家屋調査士試験合格講座 試験に出る書式ひな形50
著者:中山 祐介
定価:2,860円(税込)

おすすめ度★★★
土地家屋調査士試験の書式(記述式)の「登記申請書」を短期間で習得したい独学者に最適の、本試験で使えるひな形だけを厳選収録した実戦テキストです。
50の書式パターンを“試験で問われる形そのまま”にまとめており、記述式の得点力を効率的に底上げできます。
本書の特徴
書式問題の“型”を体得できる構成
構成は「事例 → 解説 →作成のポイント」という流れで、各ひな形ごとに、事例提示・解説・作成のポイントが示されており、「登記記録への反映例」も掲載。
つまり、登記申請の「前」と「後」で登記記録がどう変わるのかといった変化を問う出題にも対応可能。
記述式で点差がつく箇所を重点的にフォロー
ミスしやすい欄、注意すべきポイントなど、受験生が間違いやすい部分を明確に提示。
得点しやすい答案作りのコツが身につく。
初学者でも取り組みやすい“負担の少ない分量”
本試験に直結するひな形だけに絞っているため、学習負荷が大きすぎず、無理なく周回できる。
学習の進捗に合わせて使いやすい構成
最初は読み込み、慣れてきたら書き写し、最後に暗記仕上げ というステップを踏みやすいように構成されている。
独学者向け活用ポイント
登記申請書の“型”を覚える1冊として最適
いきなり過去問から始めると挫折しがちな書式(記述式)も、 本書で登記申請書の基本形をつかむことでスムーズに学習が進む。
ミス防止チェックリストとして使える
「この欄の記載を忘れがち」「この符号は混乱しやすい」など、注意点が明確にまとまっているため、直前期の確認に非常に強い。
書式(記述式)が苦手な独学者の“弱点補強”にぴったり、繰り返しが大切
書式は独学者が最もつまずきやすい分野だが、 本書を繰り返すことで基礎が早期に安定する。本試験まで何度も徹底的に繰り返してください。
書き写し学習との相性が抜群
実際に手を動かして書式を写すと、答案作成スピードが上がる。各ひな形に対して「作成のポイント」、「登記記録への反映例」が付いているため、「なぜこの登記申請書になるか」、「その登記申請をしたらどう登記記録が変わるのか」という理解まで促せます。これは独学者が陥りやすい“登記申請書だけの暗記”のリスクを減らします。
ポイント
YouTubeで著者の中山祐介氏がひな形50の動画も出しているのでぜひ活用してください!
土地家屋調査士試験のための関数電卓徹底攻略ガイド
著者:遠藤 雅守
定価:2,200円(税込)

おすすめ度★★☆
土地家屋調査士試験で得点力を上げるために必須となる「関数電卓の使い方」を基礎から実践レベルまで解説した一冊です。
初期設定の最適化、四捨五入の取扱い、複素数モードによる高速計算、時間短縮につながるキー操作など、試験に直結するテクニックを網羅しています。
測量計算の実例や豊富な例題・演習・過去問を通じて、ただ操作を覚えるだけでなく、本試験で使いこなせる“実践力”が身につく構成。
本書の特徴
関数電卓操作を基礎から体系的に習得できる構成
測量計算に必要なキー操作・関数の使い方・計算手順まで、一冊で網羅
独学者が迷いやすい計算の“理由・根拠”まで理解できる
押し方だけでなく計算順序・考え方を丁寧に補強し、理解が深まる
本試験に直結する実践力を短期間で身につけられる
三角関数・座標・面積計算の最短手順を重点的に解説し、図解・実践問題・反復学習によりスピードと正確性を強化
独学者向け活用ポイント
まずは1周して“押し方の型”を覚える
キー配置と操作順序を体で覚え、基礎操作の土台を作る
2周目で“なぜその操作をするのか”を理解する
計算の意味・根拠を押さえることで、応用問題やイレギュラー処理にも対応できる
3周目以降は“スピード重視の演習モード”へ
本試験は時間勝負。反復で操作の安定性と速さを鍛える
過去問と併用し、わからない操作は本書で随時補強する
辞書的に使えるため、過去問演習との相乗効果が高い
土地家屋調査士受験100講〔Ⅲ〕書式編
著者:深田静夫(早稲田法科専門学院)
定価:4,620円(税込)

おすすめ度★★☆
択一式でも紹介した同シリーズで、書式(記述式)対策の本格派テキスト。
書式編として、土地・建物・区分建物の登記申請書・調査記録・図面・作図・書式運用を、 基本パターンから応用問題まで網羅しているテキストです。
本書の特徴
- 本試験出題を想定した書式の “基本全パターン+応用問題” を収録
- 「問題+解説」が見開き構成でまとまっており、学習効率が高い
- 土地・建物・区分建物それぞれの登記申請書・図面作成・計算までカバー
独学者向け活用ポイント
- 書式学習の “入口”として使うのではなく、理論・申請書の基礎を押さえた後に使うことが有効
- 見開き構成の問題+解説を 何度も繰り返すことで“書式の型”が体に染みつく。問題数が多いため、反復がカギ
- 過去問・本試験形式の書式も挿入されているため、 理論学習後に本実戦演習用テキストとして活用できる
- 本試験直前期には、「何度も出る書式パターン」「ミスしやすい記載箇所」を本書から抽出して、短時間で復習可能な“重点リスト”として使う
- 書式部分は一度読んだだけでは定着しづらいため、 本書を“本試験まで繰り返し使う”書式(記述式)対策の柱教材として位置づけることが合格への近道
土地家屋調査士 記述式合格演習テキストⅠ・Ⅱ
著者:東京法経学院 編集部編
定価:20,900円(税込)※2冊セット
※書店等では販売しておらず、東京法経学院の公式サイトで購入可能です

おすすめ度★★★
記述式の“本試験レベルの事例演習”を集中的に行える、調査士試験対策では定番の実戦テキストです。
出題が複雑化する記述式に対応するために構成されており、合格に直結する「思考プロセス」「図面作成の手順」「答案の組み立て」を身につけられる教材として高く評価されています。
毎年改訂されているところは良いが、価格が高いのと書店では販売されていないところが難点。
本書の特徴
本試験レベルの“実戦事例”を豊富に掲載した記述式特化テキスト
- 土地編・建物、区分建物編ともに、基礎的な問題から始まり、典型問題や近年の複雑な事例まで幅広く収録
- 東京法経学院が蓄積してきた実戦データをもとに、実際に出題される構造に近い問題を精選
記述式で点数を伸ばすための“思考手順”が身につく構成
- 問題文の読み取り → 現況整理 → 図面作成 → 答案作成までの流れを、1問ごとに丁寧に解説
- 受験生のつまずきやすい「どこから手をつけるか」がわかり、独学でも再現できる
解説が“答案作成のプロセス”に焦点を当てており実戦的
- 単なる正解の提示ではなく、考え方の順序・検討ポイントを明確化
- 実際の本試験で要求される「処理手順」を体で覚えられる
合否を分ける“図面処理スキル”を強化できる
- 土地・建物、区分建物ともに作図の練習量を確保できるため、図面の精度が大きく向上
- 書式(記述式)問題が苦手な受験生の弱点補強に最適
複雑事例に対応できる“応用力”が身につく
- 今後の本試験で出題されると予想される複雑事例も解説されている
- 難問耐性がつくため、上位合格を狙う受験生から支持されている
- 体系書には載っていない“実戦処理のコツ”を学べる点も良い
独学者向け活用ポイント
過去問だけでは足りない“本試験レベルの演習量”を補える
- 書式(記述式)は本試験の問題数が少なく、過去問だけでは十分な練習ができない
- 本書を併用することで、基礎から応用まで質・量ともに本試験レベルの訓練が可能
解きながら“処理の型”を固めると得点力が劇的にアップ
- 各問題の「どこを見て、何を判断し、どう記述するか」を繰り返し確認することで、型が身につく
- その結果、本試験でのミス・迷いが激減する
本試験まで“繰り返し解くこと”が最重要
- 書式(記述式)は一度理解しても、時間が経つと手が動かなくなるため、繰り返し演習が必要
4、実践演習(過去問演習)
過去問集の使い方は択一式対策と書式(記述式)対策で変える必要があります。
択一式の場合、過去に出題された問題は多少の表現を変えて今後も出題される可能性が高いため、繰り返し徹底的にやることが大切です。
過去問が正しく溶けるようになれば合格点に達するため、過去問以外はやる必要はありません。できる限り効率よく学習を進めましょう。
一方で書式(記述式)の場合、同じ状況設定の問題が2度出ることはありません。
ですので、過去問は出題傾向などの分析に使用することが大切です。
当然ですが、過去に出題された問題は全て解けるようになる必要はあります。
書式(記述式)学習で大切なことは本試験レベルの問題を時間内に解き切る訓練を繰り返すことです。
詳細はこちらの記事で紹介していますので参考にしてください。
-

-
【書式(記述式)対策】土地家屋調査士試験の勉強法【目標は基準点を確実クリア】
こんにちは、はるです。 今回は書式(記述式)を中心に短期合格、1発合格のための土地家屋調査士試験の勉強法と対策を紹介します。 書式(記述式)はどのように勉強したらよいのか悩む方が多いと思います。 書式 ...
択一式のおすすめ過去問集
正直、択一式の過去問はここで紹介したものであればどれを選んでも問題はないです。
ただし、最新のものを選ぶようにしてください。
択一式の過去問は大きく2つの種類に分かれます。
- 本試験と全く同様の五肢択一式などのもの
- 選択肢をバラバラにした一問一答形式にしたもの
当然、本試験と同じ形式に慣れることは必要です。
本試験の形式に慣れたら土地家屋調査士試験の場合、選択肢をバラバラにした一問一答形式にしたもので演習を繰り返すことを私は強くおすすめします。
理由は土地家屋調査士試験では同様の論点が繰り返し出題されており、各論点を効率良く学習するには一問一答形式が有効だからです。
特に社会人など限られた時間を活用していく必要がある場合は5分の隙間時間でも取り組むことができます。
その演習におすすめなのが何度か出てきている新・合格データベースです。
次に、本試験形式のおすすめ過去問集を紹介していきます。
土地家屋調査士 択一式過去問
著者:日建学院(齊木公一)
定価:3,740円(税込)

おすすめ度★★☆
本書の内容と特徴
日建学院の定番過去問題集です。
本書は、択一式(マーク式・5択など)問題の過去問集で、過去8年分を収録しています。
科目別・テーマ別に整理されており、独学でも迷わず進められる構成が高く評価されています。
正確な知識の定着と、最新の出題傾向への対応に最適な1冊です。
最新年度分については「本試験形式で掲載」されており、実戦演習用として模試的に使える構成になっています。
土地家屋調査士 記述式過去問
著者:日建学院(齊木公一)
定価:3,960円(税込)

おすすめ度★★☆
本書の内容と特徴
こちらは上記の書式(記述式)版です。
土地の問題のコラムには「未知点算出戦略思考フロー」として、未知点の座標値を算出するための思考を養い、段取りを身につけるためのコンテンツが掲載されています。
土地家屋調査士 択一式過去問マスターⅡ 不動産登記法(土地/建物/区分建物)
著者:東京法経学院 編集部編
定価:7,810円(税込)
※書店等では販売しておらず、東京法経学院の公式サイトで購入可能です
おすすめ度★★☆
本書の内容と特徴
東京法経学院の定番過去問題集です。
量、質ともに申し分ないものとなっています。
択一式過去問マスターⅠ民法・土地家屋調査士法・不動産登記法/総論
平成元年度~令和6年度までの(昭和年代の重要問題はセレクトして収録)366問を収録。
択一式過去問マスターⅡ不動産登記法(土地/建物/区分建物)
平成元年度~令和6年度までの(昭和年代の重要問題はセレクトして収録)307問を収録。
土地家屋調査士 記述式過去問マスターⅠ<土地編>
著者:東京法経学院 編集部編
定価:8,140円(税込)
※書店等では販売しておらず、東京法経学院の公式サイトで購入可能です
土地家屋調査士 記述式過去問マスターⅡ <建物・区分建物編>
著者:東京法経学院 編集部編
定価:8,140円(税込)
※書店等では販売しておらず、東京法経学院の公式サイトで購入可能です
おすすめ度★★☆
本書の内容と特徴
東京法経学院の定番過去問題集です。
択一式過去問マスターと同様、量、質ともに申し分ないものとなっています。
記述式過去問マスターⅠ<土地編>
昭和44年度~令和6年度までの厳選された43問が収録されています。
平成元年度から令和6年度までの全問と、昭和時代の出題問題を厳選した問題について、これを分野別、項目(登記)別に整理、詳細な解説を付した記述式問題の過去問集です。
記述式過去問マスターⅡ<建物・区分建物編>
昭和44年度~令和6年度までの厳選された49問が収録されています。
平成元年度から令和6年度までの全問と、昭和時代の出題問題を厳選した問題について、これを分野別、項目(登記)別に整理、詳細な解説を付した記述式問題の過去問集です。
その他、持っておくべき教材
土地家屋調査士 六法
著者:東京法経学院 編集部編
定価:6,600円(税込)

おすすめ度★★★
本書の内容と特徴
土地家屋調査士試験で必要な法令集。
後半には先例、通達などもまとまっており、特に書式(記述式)の根拠探しに重宝します。
見やすく、実務でも使えるので非常におすすめです。
効率を上げたいなら予備校の単科講座の活用もあり
「独学をしてみたけど、難しい・・・」
「計算や作図のところだけでも正しく教わりたい・・・」
こういう方は少なくないと思います。
そこで、独学で進める方でも、苦手分野だけを単科講座で補強するのは非常に有効です。
単科講座とは、特定分野(計算方法・作図方法など)に特化した短期集中型の講座です。
必要な部分だけを補えるため、費用を抑えながら効率を高められるのが魅力です。
たとえば、アガルートの単科講座は独学との相性が良いです。
アガルートの単科講座は私も受講経験がありますが、理解が高まり、必要な範囲だけを短期間で学べる点がメリットです。
独学は「費用を抑えつつ、自分のペースで進めたい人」に最適ですが、効率を重視するなら“単科講座の併用”が近道です。
単科講座のメリット
- テキスト学習で理解しにくい部分を“映像で視覚的に理解”できる
- 最新出題傾向に沿った解説が得られる
- 自分の弱点分野だけを強化できる
特に、書式(記述式)関連の講座は独学者との得点差が大きく出る部分。
動画で「答案の作り方」を学ぶことで、理解→再現のスピードが格段に上がります。
おすすめテキストを使用した独学(+予備校の単科講座)勉強スケジュール
今まで見てきたテキストを使用した具体的な勉強スケジュールを紹介します。
予備校のおすすめ単科講座も盛り込んでいます。

ポイント
テキスト1週目はよく分からない状態でもOKなので、とりあえずテキストを終わらせること
少しでも分からないからと立ち止まると、全範囲が終わらず本試験に突入してしまいます。
最初は分からないのが当然です。
私も最初はすべてが何かの暗号かのような気持になり挫折しそうでした。
諦めず、2週目、3週目と繰り返すと自然に理解が深まっていきます。
大事なのは諦めず、学習習慣を身に着けること、そして継続することです。
それでも独学が難しいと感じたら、予備校のフルカリキュラム講座の検討も
独学は自由度が高い反面、ペース管理や理解の確認が難しくなりがちです。
独学での学習には、時間管理・モチベーション維持・理解の深掘りといった“自力では超えにくい壁”があります。
「どうしても独学では続かない」「一度挫折した」という方には、フルカリキュラム講座を検討するのも一つの方法です。
「何から手をつけていいかわからない」「毎日勉強しているのに伸びない」と感じたら、予備校のフルカリキュラム講座を検討してみましょう。
アガルートの土地家屋調査士試験講座は評判、口コミが大変良くおすすめ
私もアガルートの土地家屋調査士試験の講座受講を経験してますが、非常にわかりやすくおすすめです。
また、アガルートの講座を利用して合格したら全額返還やお祝い金も貰えたりしますので、独学での限界を感じた方は検討してみてください。
詳しくはこちらの記事も参考にしてください。
-

-
【2026年最新版】アガルートの評判、口コミを実体験から本音レビュー【土地家屋調査士試験】
評判や口コミが良いアガルートですが、実際はどうなのか。今回はアガルートの土地家屋調査士試験の講座を徹底レビューしました。私は独学、アガルート、東京法経学院で学習経験があります。良い点だけでなく悪い点も正直に徹底解剖しているので参考にどうぞ!
特に1年でも早く合格を目指すなら、「予備校のフルカリキュラム講座の活用」で最短合格を狙いましょう。
長い目で見れば、1年早く合格する=1年分の収入を早く得るという意味でも、費用以上の価値があります。
-

-
【2026年最新版】土地家屋調査士試験のおすすめ講座【実体験をもとに比較】評判・口コミは本物?
こんにちは、土地家屋調査士のはるです。 『土地家屋調査士試験に絶対合格したい!』と思っている方、ぜひ最後までご覧ください。 私は土地家屋調査士試験に合格済みで、アガルートと東京法経学院の受講経験があり ...
まとめ:独学でも、正しい教材と戦略で合格は可能
- 独学でも、正しいテキスト選びや学習手順で十分合格可能
- 費用を抑えつつ、「独学+予備校の単科講座」で効率を最大化
- 挫折しそうなら、早めに予備校のフルカリキュラム講座に切り替えるのも戦略的判断
- 最後に大切なのは、「諦めず継続する」
『完全独学』VS『独学+単科講座』VS『予備校利用(フルカリキュラム)』の比較をまとめておきます。
| 項目 | 完全独学 | 独学+単科講座 | 予備校利用(フルカリキュラム) |
|---|---|---|---|
| 総費用の目安 | 5~10万円 | 10〜40万円 | 40〜50万円 |
| 学習効率 | 非効率になりがち | 弱点補強で効率UP | 最短合格向け |
| 向いている人 | 一人で学べるタイプ 費用を抑えたい人 | 基本は独学で良いが書式に不安がある人 | 最短で確実に合格したい人 |
| 挫折リスク | 高い | 中程度(講座で補える) | 低い(学習サポートが充実) |
| 合格に必要な期間 | 1.5〜3年 | 1〜2年 | 1年(短期合格者多数) |
| 書式(記述式)の習得難度 | 非常に高い | 高いが、単科講座で改善可能 | 最も低い |
| サポートの有無 | なし | 単科講座など一部あり | 豊富(質問制度・添削・答練、模試) |
| 教材の充実度 | 市販中心で少ない | 市販書+講座教材で最適化 | オリジナル教材で体系的 |
| メリット | コスト最安 自分のペースで進められる | 費用対効果が非常に高い 弱点補強に最適 | 学習迷子にならず最短ルートで済む |
| デメリット | 書式が壁になりやすい | 費用が増える 講座選びが必要 | 費用が高額 |
2026年、あなたの学習が最短ルートで実を結び、土地家屋調査士として新しい一歩を踏み出せるよう、正しい教材と学習戦略を選びましょう!
応戦しています!


-425x600.jpg)



-150x150.png)
