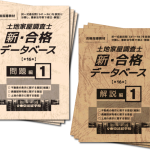こんにちは、土地家屋調査士のはるです。
「40代からまったくの未経験で、土地家屋調査士を目指しても大丈夫なのか?」
「法律の勉強なんてしたことがないし、試験も仕事も難しそう…」
そんな不安を抱く方は多いと思います。
実際に私も、業界に入る前は同じように「今の年齢から本当に通用するのか」と悩みました。
しかし、結論から言えば、40代・未経験からでも土地家屋調査士を目指すことは十分に可能です。
そして、この仕事には年齢を重ねた人だからこそ発揮できる強みがあります。
近年、土地家屋調査士を目指す人の年齢層は幅広く、30代後半〜40代で資格取得を目指す社会人も増えています。
建築や不動産業界からの転職はもちろん、まったく別の業種から挑戦する人も少なくありません。
土地家屋調査士は「一生食べていける国家資格」と言われることも多く、独立開業ができる点や、自分の裁量で仕事を進められる点に魅力を感じる方が多いでしょう。
とはいえ、試験の難易度や実務のリアルな厳しさを知らずに飛び込むと、途中で挫折してしまうこともあります。
そこで本記事では、現役の土地家屋調査士である私が、40代・未経験から資格取得・実務デビューまでの道のりを、できるだけリアルにお伝えします。
「今からでも遅くないのか」「どうやって勉強すればいいのか」「実際に働けるのか」
そんな疑問をひとつずつ解消していきましょう。
土地家屋調査士とは?資格の概要と求められる専門性
土地家屋調査士という名前を聞いても、どんな仕事をするのか具体的にイメージしづらい方も多いと思います。
まずは、資格の基本から整理しておきましょう。
不動産登記の専門家としての役割
土地家屋調査士は、土地や建物の「物理的な状況」を登記する専門家です。
たとえば、土地の境界を明確にしたり、新しく建てた建物の位置や形状を図面にして法務局に申請したりします。
一言でいえば、「不動産の形を登記記録に反映させる仕事」。
法律的には「不動産登記法」に基づく国家資格で、司法書士と同様に法務省が管轄です。
現場と法律、両方を扱うハイブリッドな仕事
土地家屋調査士の仕事は、デスクワークとフィールドワークが半々くらいの割合です。
現場では測量機械などを使って土地の境界や建物の位置を正確に測り、 事務所では登記申請書や図面を作成し、法務局に提出します。
そのため、法律の知識だけでなく、測量の技術やCAD(製図ソフト)のスキルも必要になります。
と聞くと「専門的で難しそう」と思われるかもしれませんが、安心してください。
実務で使う知識や技術は、資格取得後に一つずつ身につけていけるものです。
社会に求められ続ける資格
土地家屋調査士は、不動産取引がある限り需要がなくならない資格です。
新築・相続・売買・開発といった不動産の動きに必ず関わるため、景気に左右されにくいのが特徴です。
また、高齢化、相続問題、空き家問題などの増加により、「境界トラブルの専門家」としての役割も年々大きくなっています。
社会的な信頼性が高く、地域に根ざして長く続けられる仕事でもあります。
40代・未経験でも挑戦できる3つの理由
「今からじゃ遅いかもしれない」
土地家屋調査士を目指す40代の方から、よくそんな言葉を聞きます。
ですが、私は声を大にして伝えたいのです。
40代だからこそ、土地家屋調査士に向いている部分がたくさんあるということを。
ここでは、その理由を3つに分けてお話しします。
理由① 年齢制限がなく、資格そのものに“入り口の壁”がない
土地家屋調査士試験には、年齢や学歴、実務経験といった制限が一切ありません。
つまり、「やる気がある人なら誰でも目指せる資格」です。
もちろん、試験の難易度は決して低くありません。
ですが、40代だからといって不利になることはまったくありません。
実際に私の知る合格者にも、40代・50代で初挑戦から合格した方がたくさんいます。
この資格の世界は、スタートが遅い人ほど努力の質が高い傾向があります。
「時間を無駄にできない」という意識がある分、計画的に学ぶ力が強い。
その姿勢が、結果的に合格を引き寄せるケースも多いのです。
理由② 社会人として培った経験が“現場での強み”になる
土地家屋調査士の仕事は、現場測量だけでなく、 お客様や隣地の方、行政担当者、司法書士など、多くの人とのやり取りで成り立っています。
たとえば、立会の場面では「境界線はどこなのか」という話し合いが行われます。
相手の主張を聞き取り、調整し、納得してもらう必要もあります。
ここで求められるのは、まさに社会人としての“対人スキル“です。
また、複数の案件を並行して進めるため、
スケジュール管理や段取り力も非常に重要です。
私が補助者として働き始めた頃、測量の経験はゼロでした。
でも、営業職時代に培った「段取りと報連相の基本」が思った以上に役立ちました。
現場で学ぶ技術や知識は後からいくらでも身につけられます。
それよりも、人との信頼関係を築く力こそが、この仕事の本質です。
理由③ 独立・開業ができる実務資格。40代だからこそ“第二のキャリア”に最適
土地家屋調査士は、資格を取れば個人で開業できる国家資格です。
つまり、会社に雇われず、自分の名前で仕事を受けられる。
この点が、他の資格や転職とは大きく異なります。
40代という年齢は、これまでの経験を踏まえて「今後の人生をどう働きたいか」を真剣に考える時期でもあります。
もしあなたが、
「このまま会社員として働き続けるのは不安」
「自分の力で仕事をしていきたい」
と感じているなら、土地家屋調査士はその答えになり得る資格です。
もちろん、資格を取ってすぐに独立は簡単ではありません。
多くの人は、まず補助者として事務所に入り、実務を覚えながら経験を積みます。
ただし、努力次第で数年後には独立し、地域に根ざした仕事を続けることも十分可能です。
私自身も最初は補助者として働きながら、仕事の流れを覚えていきました。
測量現場での失敗も多く、最初の1年は戸惑いの連続でした。
でも、「現場で汗をかいた経験」と「お客様の声を直接聞けたこと」が、いまの自分の強みになっていると感じています。
40代で新しい資格に挑戦するというのは、勇気のいる決断です。
ですが、これまで培ってきた経験は、必ずこの仕事で生きてきます。
未経験でも、遅すぎることはありません。
むしろ、人生の“第二のスタートライン”として最適なタイミングだと私は思います。
働きながら合格を目指すための現実的な学習プラン
40代で土地家屋調査士を目指す多くの方は、仕事や家庭と両立しながらの勉強になると思います。
「時間がない」「続かない」「何から手をつければいいか分からない」
そんな声を本当によく聞きます。
実際、土地家屋調査士試験の最大の壁は「内容の難しさ」よりも、継続して勉強を続けることの大変さです。
私自身も、仕事の合間や子どもが寝たあとに少しずつ勉強を進めました。
毎日3時間勉強するなんて現実的ではありません。
でも、短い時間でもコツコツ続けることで、確実に力はついていきます。
働きながら合格を目指す現実的な学習プラン
「働きながら土地家屋調査士試験に合格するなんて無理かも…」
そう感じる方は多いと思います。私も最初はそうでした。
でも、結論から言えば働きながらでも十分に合格可能です。
ポイントは、勉強のやり方を“戦略的に組み立てる”こと。
時間をいかに確保するか、どの教材をどう活用するか、効率よく学ぶ工夫が大切です。
1. 勉強時間の現実と確保の工夫
土地家屋調査士試験の合格者の平均学習時間は、概ね800〜1,000時間程度と言われています。
社会人が働きながら1年で合格を目指す場合、1日あたり2〜3時間を確保する計算になります。
私は、平日は仕事後に1〜2時間、休日にまとめて3〜4時間勉強するスタイルで進めました。
ポイントは、短時間でも集中して学ぶこと。
長時間ダラダラと机に向かうより、30分〜1時間のまとまった学習を何回も繰り返すほうが効率的です。
2. 通信講座やオンライン教材の活用
働きながら勉強する場合、通学型より通信講座やオンライン教材の活用がおすすめです。
私も予備校の通信講座を利用しました。
理由は、以下の通りです:
- 自宅で好きな時間に学べる
- 動画やテキストで繰り返し復習できる
- 模擬試験や過去問演習も効率的
特に動画講義は、「目で見て、音で聞いて理解できる」ので、法律知識ゼロの方にも分かりやすいです。
私自身も最初は法律の専門用語に戸惑いましたが、動画を繰り返すことで少しずつ理解できるようになりました。
こちらの予備校の記事も参考にしてください。
-

-
【2026年最新版】アガルートの評判、口コミを実体験から本音レビュー【土地家屋調査士試験】
評判や口コミが良いアガルートですが、実際はどうなのか。今回はアガルートの土地家屋調査士試験の講座を徹底レビューしました。私は独学、アガルート、東京法経学院で学習経験があります。良い点だけでなく悪い点も正直に徹底解剖しているので参考にどうぞ!
3. 1年間で合格を目指す学習スケジュール例
私が実践したのは、平日・休日でメリハリをつけるスケジュールです。
平日(1〜2時間)
- 移動時間や休憩時間にテキストやスマホ(学習範囲をスマホに入れていた)を確認
- 夜、子どもが寝たあとにテキストの1単元でも読む
休日(3〜4時間)
- 過去問演習と解説の確認
- 書式問題の演習(まとまった時間が確保できる時)
- 弱点箇所を重点的に復習
このように小さな時間を積み重ねることで、1年で合格レベルに到達できます。
私は、仕事と家庭の隙間時間を意識的に活用しました。
「毎日30分でも触れる」ことを習慣化するのが最大のポイントです。
4. 挫折しないための工夫
働きながらの勉強で一番の敵は、「挫折」です。
40代の場合、家庭や仕事の責任もあり、学習が中断しやすくなります。
そこで、私が実践していた方法をいくつか紹介します。
目標を細分化する
「1日1章」「週末に過去問1回分」といった小さな目標に分けると、達成感が積み重なります。
仲間やSNSで進捗を共有する
同じ試験を目指す仲間に学習内容を報告すると、モチベーションが維持できます。
休む日もスケジュールに組み込む
無理に毎日勉強しようとすると逆効果。疲れたら休むことも計画の一部にします。
現場経験と結びつけて理解する
測量や図面作成の学習は、実際の補助者経験とリンクさせると記憶に残りやすいです。
私は、実務の話を思い出しながらテキストを読むと理解が早まりました。
5. 継続力が最大のカギ
働きながらの勉強は、継続力がすべてです。
1日30分でも毎日続けること。
週末にまとめて復習すること。
40代のあなたには、社会人経験で培った計画力や忍耐力があります。
それを学習に活かせば、確実に合格に近づけます。
合格後のキャリア|未経験から調査士補助・独立へ
土地家屋調査士試験に合格した後、多くの40代未経験者が抱く疑問はこうです。
「実務経験がない自分でも働けるのだろうか?」
「独立・開業までの現実はどうなっているのだろうか?」
私自身も、合格直後は不安でいっぱいでした。
資格は取得できても、現場経験がなければ仕事は回せません。
そこでまず経験を積むのが、土地家屋調査士事務所での補助者勤務です。
未経験でも働ける理由
補助者として働く場合、最初からすべてを一人でこなす必要はありません。
現場では、先輩調査士の指示に従いながら測量や図面作成を学びます。
最初は測量機器の操作やCAD操作などの簡単な作業から始め、少しずつ範囲を広げていくのが一般的です。
私も初めて補助者として現場に出たとき、測量の知識はゼロでした。
それでも、現場での実践と先輩のアドバイスを組み合わせることで、1年ほどで基本的な案件は一人で対応できるレベルになりました。
1日の仕事の流れ(例)
土地家屋調査士の1日は、現場と事務作業の両方で構成されます。
例えば
午前:現場測量
依頼者や隣地所有者にご挨拶
現地測量
メモや写真で記録を整理
午後:事務所での作業
測量データをもとにCADで図面作成
登記申請書の作成や書類整理
先輩調査士のチェックを受けて修正
こうして現場と事務所の両方を経験することで、実務力が確実に身についていきます。
未経験からでも、段階を踏めば現場で自信を持てるようになるのです。
独立・開業のリアルなタイミング
多くの土地家屋調査士は、まず補助者として2〜3年経験を積んだ後に独立します。
最近は土地家屋調査士法人も増えてきており、組織の中で土地家屋調査士として働く方も多いです。
独立のタイミングは人それぞれですが、ポイントは「案件を自分で回せる自信」と「営業ルートの確保」です。
開業初年度は売上が安定せず不安もあるかと思いますが、経験と人脈の積み重ねが収入の安定につながります。
独立後の収入イメージ
土地家屋調査士の収入は、経験と案件の数に大きく依存します。
一般的な目安として:
補助者時代:月20〜(勤務先・地域による)
補助者でも経験実績次第では一般できなサラリーマンよりも高収入は可能です。
独立後、軌道に乗ると:月100万円以上も十分可能
もちろん、最初から高収入を狙うのは現実的ではありません。
補助者として着実に経験を積み、人脈ネットワークを広げ、地域に信頼を築くことが長期的な収入安定の鍵です。
未経験者に伝えたいこと
40代未経験であっても、資格取得後のキャリアは十分に描けます。
ポイントは以下の通りです:
- 焦らず段階を踏む
- 最初は補助者として現場とデスクワークを経験する
- 徐々に担当数を増やす
- 実務と学習をリンクさせる
- 知識が実務で生きる感覚をつかむ
- 営業ルートを意識する
- 人脈ネットワークを広げる
私自身も、業界未経験でスタートしましたが、最初の苦労が間違いなく現在の力になっています。
40代から土地家屋調査士を目指す上での注意点と乗り越え方
40代・未経験で土地家屋調査士を目指す方にとって、資格取得や実務経験の道のりは決して平坦ではありません。
ここでは、私自身の体験と周囲の事例をもとに、注意すべきポイントとその乗り越え方をまとめます。
注意点① 勉強と仕事・家庭の両立は容易ではない
40代の場合、仕事の責任や家庭の役割も増えるため、勉強時間の確保が最初の壁です。
私も、子どもが寝たあとや通勤時間、休憩時間を使って学習する日々が続きました。
乗り越え方は、「学習のルールを明確化する」ことです。
- 平日は30分〜1時間を集中学習
- 休日に2〜3時間まとめて復習
時間の絶対量よりも、毎日継続する習慣を作ることが合格のカギです。
注意点② 新しい知識の吸収には時間がかかる
法律や測量の知識は、初めて触れる方には専門用語や概念が難しく感じます。
特に40代の場合、記憶力や理解力のスピードに不安を感じることもあるでしょう。
私の対策は、実務と結びつけながら学ぶことでした。
測量現場や建物登記の実務での体験を振り返って理解を深める
こうすることで、単なる暗記ではなく、実務で生きる知識として定着します。
実務と資格勉強の違いもあるので注意は必要です。
注意点③ モチベーションの維持が難しい時期がある
働きながら学習していると、どうしても疲れやストレスでやる気が下がることがあります。
私も試験直前に「もう間に合わないかもしれない」と感じたことがありました。
この乗り越え方としては、小さな達成感を積み重ねることが有効です。
- 1日1章クリア
- 過去問1回分完了
- 書式1問完了
達成した内容をリスト化すると、自分の進歩が見える化され、自然とモチベーションが回復します。
注意点④ 現場経験のギャップに戸惑う
補助者として現場に出ると、学習で理解していた知識と実務内容との差に驚くことがあります。
乗り越え方は、完璧を目指さず「経験で覚える」姿勢を持つことです。
- 失敗しても先輩に確認
- 次に同じ場面が来たら改善
- 一歩ずつ自信を積み上げる
経験の積み重ねこそが、40代未経験者の強みを引き出します。
注意点⑤ 家族との時間や健康管理も意識する
40代の場合、家庭や健康面の負担も考慮しなければなりません。
無理な勉強や長時間労働は体調不良や家庭トラブルにつながります。
私の場合は、勉強時間の確保と家庭の時間のバランスを明確化しました。
- 休日は子どもとの時間を優先
- 体調不良時は学習内容を軽くする
大切なのは、焦らず段階を踏むことと、自分の経験や強みを活かすことです。
40代だからこそ、豊富な社会人経験が現場で活きるのです。
まとめ・40代未経験から土地家屋調査士を目指す価値
この記事では、40代未経験から土地家屋調査士を目指す方に向けて、私自身の体験を交えながら、資格取得から独立までのリアルな道のりを解説してきました。
ポイントを整理すると、以下の通りです。
1. 40代でも挑戦できる理由
- 土地家屋調査士には年齢制限がなく、資格取得の“入り口”は誰にでも開かれている
- 社会人として培った経験は、現場での調整力や段取り力として強みに変わる
- 独立資格として、40代からの第二のキャリアに最適
この3点は、40代未経験者が資格に挑戦する大きな後押しになります。
年齢を理由にあきらめる必要はありません。むしろ、人生経験が武器になるのです。
2. 働きながら合格を目指す戦略
平日1〜2時間、休日にまとめて3〜4時間の学習
通信講座や動画教材の活用で効率的に学習
過去問演習と実技演習を繰り返す
私自身も、仕事と家庭の合間でこの方法を実践しました。
「短時間でも毎日触れること」が、1年で合格レベルに到達する最大のポイントです。
3. 補助者経験の重要性
- 現場での経験が、知識を実務力に変える
- 人脈ネットワークを広げ、信頼関係を築くことで独立後の仕事につながる
資格を取得しても、実務経験がなければ現場は回せません。
未経験だからこそ、補助者としての学びを大切にしましょう。
段階を踏むことで、確実に自信を積み上げることができます。
4. 40代ならではの注意点と乗り越え方
- 勉強と仕事・家庭の両立
- 新しい知識の吸収の難しさ
- モチベーション維持の工夫
- 現場経験とのギャップ
- 家族や健康の管理
これらは40代未経験者が直面しやすい課題ですが、戦略と工夫で乗り越えられます。
私も同じ道を歩み、毎日の学習の積み重ねと現場経験、家族の理解で乗り越えることができました。
5. 挑戦の価値と心構え
土地家屋調査士は、知識だけでなく実務力と人間力が問われる資格です。
40代で未経験から挑戦することは、確かに勇気がいる決断です。
しかし、社会人としての経験、計画力、忍耐力を活かせば、必ず道は開けます。
ポイントは、以下の通りです:
- 焦らず段階を踏む:補助者としての経験を大切に
- 継続する習慣を作る:短時間でも毎日学習
- 経験を強みに変える:現場での学びを資格取得に活かす
- 人脈と信頼を築く:将来の独立・開業につなげる
40代だからこそ、経験と知識の両方を活かして新しいキャリアを作れるのが土地家屋調査士です。
未経験からでも挑戦は可能です。この記事を読んで、少しでも「自分にもできるかもしれない」と感じたなら、それが一歩を踏み出すタイミングです。
あなたも、40代からの挑戦で新しい人生を切り拓くことができます。
資格取得から補助者経験、勤務土地家屋調査士または独立・開業までのステップを意識しながら、計画的に学んでいきましょう。
この記事を通じて、40代・未経験から土地家屋調査士を目指す方が、現実的な道筋を理解し、前向きに一歩を踏み出せることを願っています。
-2.jpg)

-150x150.png)